◎阿賀川の歴史に学ぶ学習会バスツアー活動報告 R7.10.30
10月22日(水)に、阿賀川の歴史に学ぶ学習会バスツアーを開催いたしました。
当日、朝方の気温が低く寒さを感じましたが、後に晴れ間も見え、暖かい
気候と、紅葉が始まっている景色の中でのバスツアーとなりました。
河川防災ステーションで阿賀川の防災について学習して災害対策車を見学し、
奥会津ビジターセンターでは奥会津の魅力や会津の歴史について学習しました。
また、奥会津水力館では水力発電の特徴や歴史的意義を深く知り、
本名ダムでは洪水吐ゲート上屋に上り、発電所では発電機などを見学しました。
参加者によるアンケートでは、今回のバスツアーも高評価をいただきました。
事故もなくスケジュールを運べましたのも、参加者の皆様や関係各所の皆様の
ご理解とご協力があったからと心より感謝申し上げます。
今回のツアーで体験したことを多くの方に伝えていただき、もう一度現地を訪れるなど
さらに関心をもっていただけたら幸いです。
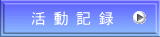
◎バスツアーの参加受付終了について R7.10.3
「阿賀川と只見川の利水・防災学習バスツアー」に沢山のご応募をいただき、ありがとうございました。
おかげさまをもちまして、定員に達しましたので、受付を終了させていただきます。
尚、今回のバスツアーに参加される皆様には、日程表などの案内を郵送いたしました。安心・安全に
ツアーを実施するため、参加に関する注意事項をお読みいただきますよう、よろしくお願いいたします。
◎阿賀川の歴史に学ぶ学習会バスツアー参加者募集! R7.8.20
10月22日(水)に、「2025 阿賀川の歴史に学ぶ学習会バスツアー」を開催します。
河川防災ステーション、奥会津ビジターセンター、奥会津水力館、本名発電所などを見学し、
利水や防災などについて学習します。昼食は道の駅かねやまで自由食(持参可)となり、参加費は無料です。
会津歴史観光ガイド協会理事長でもある、当会の石田明夫理事長がメインガイド
をつとめ、魅力ある会津の歴史や川の文化についても楽しく説明いたします。
皆様のお申し込みを、お待ちしております。
※警報発令により中止となる場合がございますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
また、階段の上り下りや徒歩での移動などが多数ありますので、あらかじめご了承ください。
日 時 :令和7年10月22日(水) 8時40分集合、16時30分解散予定
集合場所:道の駅あいづ 湯川・会津坂下 第二駐車場
参 加 費 :無料(昼食は道の駅かねやまで自由食となります)
定 員 :40名程度
申込方法 :応募者全員分の氏名・年齢・住所・電話番号を明記し、
ハガキ・メール・FAXで下記の応募先までお送りください。
応募期間:8/20〜定員になりしだい締切り(先着順)
通知方法:9月下旬頃に、該当者及び落選者へお知らせを送付します。
◎応募先
特定非営利活動法人 会津阿賀川流域ネットワーク
〒965-0856
福島県会津若松市幕内東町10-12
FAX 0242-27-2922
メール agaーriver★aabn.or.jp
(★を@に変えてお送りください)
※ツアーのスケジュールは、下記のチラシをご参照ください
|
会津阿賀川流域ネットワークは、福島県会津地方の阿賀川流域で活動する
水環境と関わる地域活動団体の参加で設立/運営しています。
阿賀川は、会津盆地では「大川」と呼ばれ親しまれています。下の写真は、会津盆地を北側から見たもので、中央に阿賀川が位置しています。
阿賀川とは、江戸時時代には「揚川」と書いていました。 現在では、福島県の会津地方は「阿賀川」と呼び、県を境に新潟県では「阿賀野川」と呼び区別しています。
江戸時代に会津藩が編纂した『新編会津風土記』には、南会津の源流から田島までは「荒海川」、田島から下郷町湯野上までを「大川」、湯野上から会津美里町本郷までを「鶴沼川」、本郷から下流を「大川」、只見川と合流すると「揚(あがの)川」と呼んでいると書かれています。
また、江戸時代に書かれた『会津旧事雑考』には、「大川」の下流でも会津若松市北会津町蟹沢付近を「蟹川」、湯川村佐野付近を「佐野川」と書かれています。
江戸時代に書かれた藩の命により会津藩士が書いた『会津鑑』には、「揚(あが)川」は、尾瀬沼を出て、只見までを「揚川」、只見から下流を「只見川」、会津坂下町片門から下流をまた「揚川」というとも書かれています。 会津の川は、すべて新潟県境の西会津の阿賀川に集まり、銚子の口(酒のお銚子のように首が狭くなってい事から名づけられています)から新潟県境に流れていきます。
時代により、川の呼び名は変化しましたが、地域の生活に密接な関係があります。
写真2段目は猪苗代湖(イとは「水」、「ナワ」とは奈良盆地のような平な場所、「シロ」とは高いを意味する大和言葉で、高い平らなところにある湖を指します)と磐梯山(「磐」とは神様が住むところ、「梯」ははしごで、神様が住むところまでつながる梯子のような山を意味します)で、会津のシンボルです。
|
|

中央が阿賀川(大川) 会津盆地中央から盆地南側を見た風景

会津若松市湊町中田から見た磐梯山1816メートル 猪苗代湖は標高514メートル

桧原湖から見た裏磐梯 標高823メートル、1888年7月15日爆発。
この時、赤十字が世界で初めて戦争以外で、けが人の救助にあたりました。
裏磐梯と命名されて、2020年は、ちょうど100年目にあたります。
中央の窪みに小磐梯山(現山頂より少し低かった)があり、それが吹き飛びました。
磐梯山の標高は、1816メートルです。桧原湖は標高823メートルです。
大小約500ほどの湖沼があります。与謝野晶子も訪れています。
加盟団体へのリンク  はホームページへリンクします はホームページへリンクします
 阿賀川・川の達人の会 阿賀川・川の達人の会  会津大川の会 会津大川の会  会津非出資漁業協同組合 会津非出資漁業協同組合
 阿賀川非出資魚業協同組合 阿賀川非出資魚業協同組合  北会津ホタルをまもる会 北会津ホタルをまもる会  田付川の清流を守る会 田付川の清流を守る会
 日本野鳥の会会津支部 日本野鳥の会会津支部  会津津ユネスコ協会 会津津ユネスコ協会
−事務局−
〒965−0856 福島県会津若松市幕内東町10番12号
TEL 0242−27−2921 FAX 0242−27−2922

|

